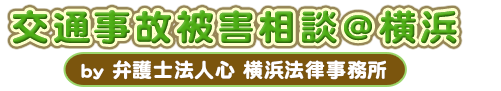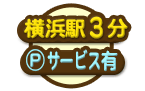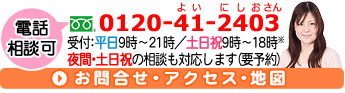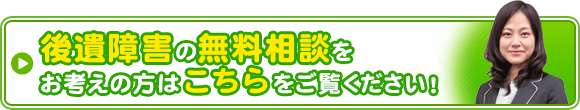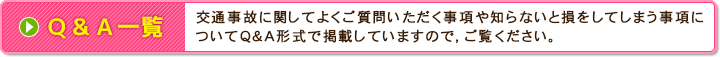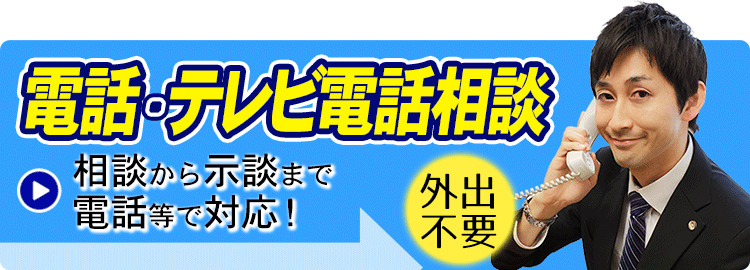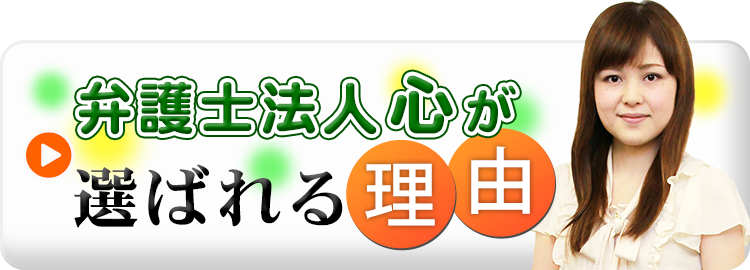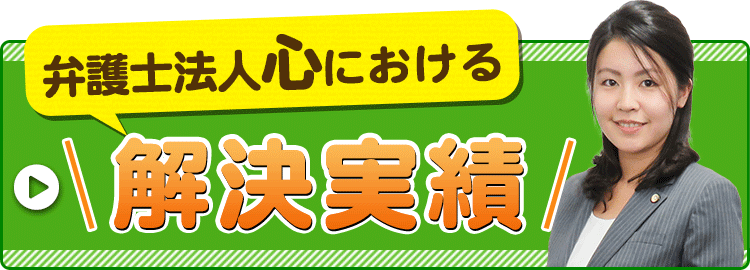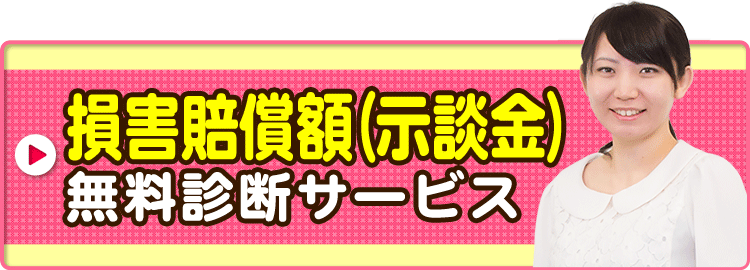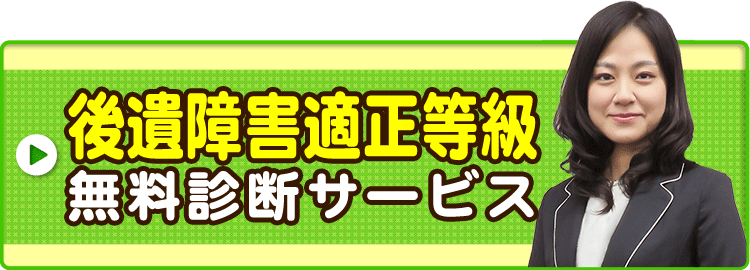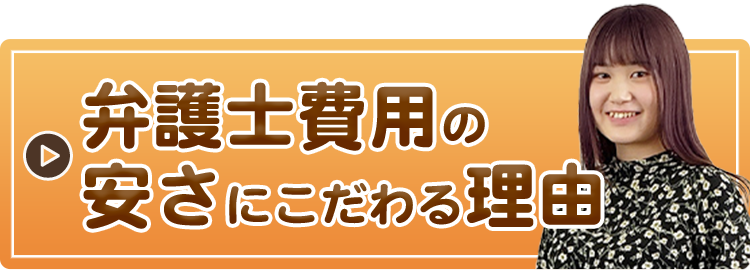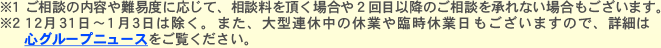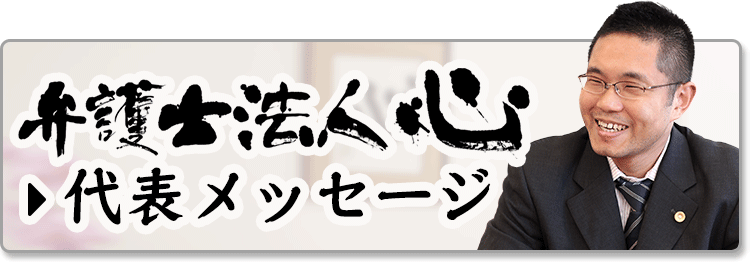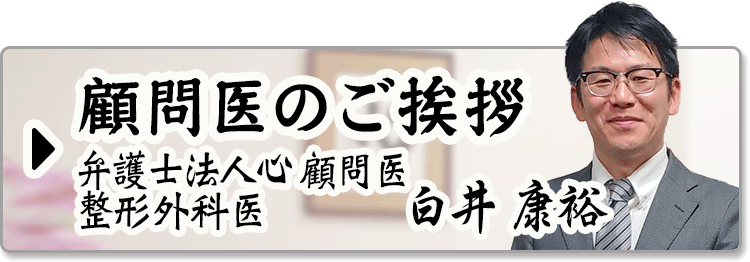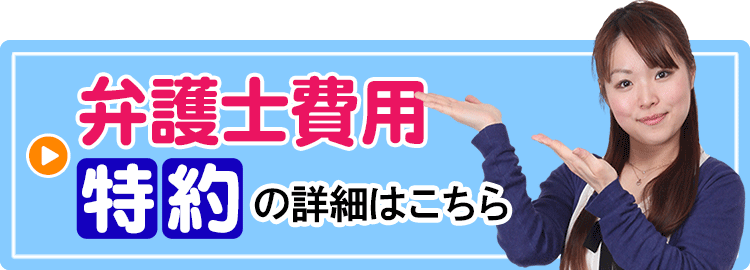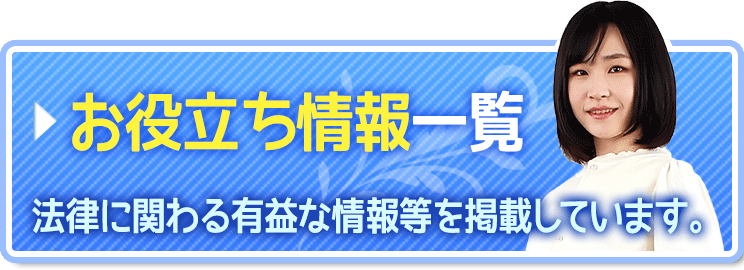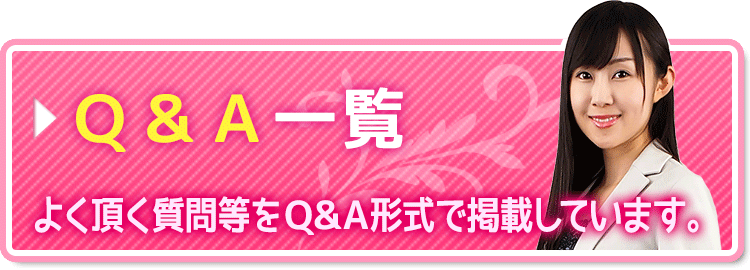後遺障害が残った場合の逸失利益
1 交通事故による損害
交通事故による損害として、一般的に発生する項目は、治療費、通院交通費、休業損害及び通院期間に対応した慰謝料となります。
これに対し、治療終了後も後遺障害が残ったことが認定されると、上記各項目とは別に、後遺障害を理由とする慰謝料と、逸失利益について、事故の相手方に請求することができます。
2 逸失利益について
逸失利益とは、後遺障害により労働能力が低下し、これに応じて労働による収入が減少したことに対する賠償金のことです。
例えば、頸椎捻挫・腰椎捻挫などのけがを負い、治療を続けたものの痛みが残った場合、痛みが残ったことを理由に後遺障害が認定されることがあります。
後遺障害が認定されると、一部例外はありますが、これに伴い労働による収入が減少すると考えられており、その減収分を逸失利益として請求することになります。
ただし、逸失利益は「労働による収入の減少」であるため、高齢者などのように、就労しておらず、労働による収入がない場合には、逸失利益の請求はできません。
3 逸失利益の算定方法の原則
後遺障害が認定されると、後遺障害の種類、程度に応じて後遺障害等級(最も重い後遺障害について1級、最も軽い後遺障害について14級)が定められており、かつ、各等級ごとに労働能力喪失率が定められています。(例:後遺障害14級であれば、労働能力喪失率は5%)
逸失利益の算定は、被害者の年収×労働能力喪失率×喪失期間に応じたライプニッツ係数にて算定されます。
4 逸失利益が発生しない場合
逸失利益は、「後遺障害により労働による収入が減少したこと」が前提となっています。
このため、単に傷跡が残っただけであり、労働そのものには影響がない場合や、公務員などのように減収が生じにくい給与のしくみなっている場合には、後遺障害が認定されても、逸失利益は認定されないことがあります。
ただし、逸失利益が認められない場合でも、慰謝料は所定の額が支払われるのが通常です。
また、事案によっては、逸失利益を認めない代わりに、慰謝料額を通常より高めに算定して賠償することもあります。
5 労働能力喪失率が低くなる場合
脊柱が骨折したことで、脊柱が変形した場合、後遺障害等級の基準では、労働能力喪失率は20%以上とされています。
しかし、変形による影響は個人差が大きいこと、デスクワークと肉体労働とでは、後遺障害による仕事への影響が異なることから、所定の労働能力喪失率よりも低い喪失率にて逸失利益が算定されることがあります。
6 労働能力喪失期間が限定される場合
後遺障害が認定された場合の労働能力喪失期間は、多くの場合、事故時の年齢から、労働可能年齢とされる67歳までとします。
しかしながら、痛みを理由とする後遺障害については、多くの場合、事故から時間が経過するにつれ、痛みの程度は軽減すると考えられています。
このため、例えば、頸椎捻挫(いわゆる、むち打ち症)による後遺障害が認められた場合、労働能力喪失期間を数年程度とする場合があります。
遷延性意識障害における損害賠償金について 高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ